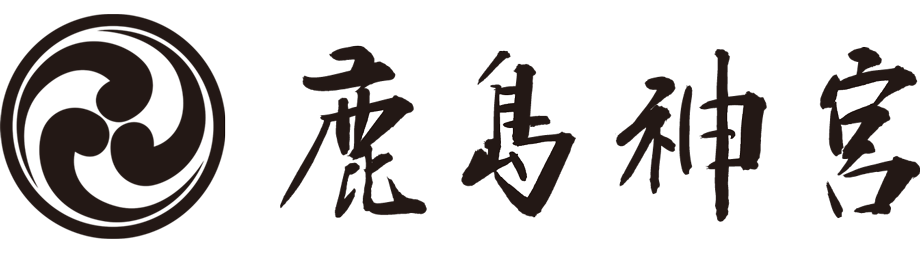東京ドーム15個分に及ぶ境内地には、透き通る湧水で禊も行われる御手洗池や鹿園など、多くのみどころがあります。
境内案内図
図上の名称をクリックすると詳細が表示されます。
 御手洗池口鳥居東日本大震災より9年と5か月の時を経てついに鹿島神宮の御手洗池口の鳥居が竣工となりました。 鋼板製ながら木造鳥居の様式にならい部材元末の直径差を再現。 奉納者発案により銘板および沓石(亀腹石)にQRコードを設置しております。
御手洗池口鳥居東日本大震災より9年と5か月の時を経てついに鹿島神宮の御手洗池口の鳥居が竣工となりました。 鋼板製ながら木造鳥居の様式にならい部材元末の直径差を再現。 奉納者発案により銘板および沓石(亀腹石)にQRコードを設置しております。 樹叢
樹叢鹿島神宮の樹叢は、茨城県指定の天然記念物です。広大な森には杉のみならずシイ・タブ・モミの巨樹が生い茂り、その種類は600種以上にも及びます。生育南限と北限の植物が混ざっているのも大きな特徴です。
 要石
要石地中深くまで埋まる要石が、地震を起こす鯰の頭を抑えていると古くから伝えられています。水戸の徳川光圀公がどこまで深く埋まっているか確かめようと7日7晩にわたって掘らせたものの、いつまで経っても辿り着くことができなかったばかりか、怪我人が続出したために掘ることを諦めた、という話が黄門仁徳録に記されています。
 御手洗池
御手洗池1日に40万リットル以上の湧水があり、水底が一面見渡せるほど澄みわたった池です。昔は参拝する前にここで禊をしました。現在では、年始に200人もの人々が大寒禊を行います。
 摂社 奥宮
摂社 奥宮御祭神 武甕槌大神荒魂 現在の社殿は、慶長10年(1605)に徳川家康が関ヶ原戦勝の御礼に現在の本殿の位置に本宮として奉納したものを、その14年後に新たな社殿を建てるにあたりこの位置に遷してきたものです。
 奥参道
奥参道奥宮に向かって300m程伸びる奥参道は鬱蒼とした巨木に覆われ、荘厳な雰囲気を醸し出しています。
5月1日には流鏑馬神事が執り行われます。 鹿園
鹿園国譲り神話において、鹿の神である天迦久神が、天照大御神の命を武甕槌大神に伝える重要な役割を担ったことから、現在でも鹿が神の使いとして大切にされています。また、奈良に春日大社を創建する際も、鹿島の神様の御分霊を鹿の背中に乗せてお遷ししたと伝わり、その道中には江戸川区「鹿骨」など鹿に関する地名が今も残っています。
 御神木
御神木鹿島神宮の森で最も古く、最も大きい木がこのご神木です。高さ約40メートルに及ぶ杉で、樹齢は約1,300年を数えます。
 芭蕉句碑
芭蕉句碑「この松の実生(みばえ)せし代や神の秋」という『鹿島紀行』中の句が刻まれています。
 親鸞上人旧跡
親鸞上人旧跡 末社 熱田社
末社 熱田社御祭神 素盞嗚尊・稲田姫命 須賀社と同じく素盞嗚尊をお祀りしています。明治以前は七夕社といっていました。
 鹿島神宮園地御手洗公園
鹿島神宮園地御手洗公園池や遊歩道が整備された静かな公園です。江戸時代までは御手洗涼泉寺がありました。
 末社 大黒社
末社 大黒社御祭神 大国主命 明治以降に鎮座された比較的新しい社です。夏越祓の日、西瓜を供えて参拝する習わしがあります。
- 祈祷殿・社務所
建物内に神殿を備えており、大勢の方に快適な環境で御祈祷をお受けいただけます。神職が普段仕事をする社務所もこの中です。
 楼門
楼門日本三大楼門の一つに数えられる楼門は、高さ約13m、重要文化財に指定されています。寛永11年(1634)、水戸徳川初代藩主の頼房卿により奉納されました。『鹿嶋社楼門再興次第記』によれば、三代将軍家光公の病気平癒を頼房卿が大宮司則広に依頼し、家光公が快方に向かった為に奉納されたとあり、浅草の水戸藩下屋敷で130余人の大工が切組み、船筏で運んで組み立てました。昭和15年の大修理の際丹塗りとし、昭和40年代に檜皮葺の屋根を銅板葺にしました。
 授与所
授与所多くの種類の御守・御札等を授与しております。
授与時間 毎日8:30~16:30  摂社 高房社
摂社 高房社御祭神 建葉槌神 武甕槌大神の葦原中国平定に最後まで服従しなかった天香香背男を抑えるのに大きく貢献した建葉槌神が御祭神です。
古くから、まず当社を参拝してから本宮を参拝する習わしがあります。 仮殿
仮殿元和4年(1618)、社殿造営のため徳川2代将軍秀忠公が奉納しました。まずこの仮殿に神様をお遷ししてから、旧本殿を奥宮まで曳いていき、その跡地に新しい社殿を造営したのです。
江戸時代は楼門を入った真正面にあり、その後2回の移動で現在の場所となりました。
 本殿・石の間・幣殿・拝殿
本殿・石の間・幣殿・拝殿本殿・石の間・幣殿・拝殿の4棟からなる社殿は、元和5年(1619)、徳川2代将軍の秀忠公が寄進したもので、重要文化財に指定されています。
本殿は参道から見て一番奥にある三間社流造の建物で、御祭神の武甕槌大神をお祀りしています。
拝殿は手前に見える建物で、正式参拝や結婚式の際にお上がりいただくことができます。
 さざれ石
さざれ石 工作場
工作場境内の木造造作物を一手に担う工作場です。
 末社 御厨社
末社 御厨社御祭神 御饌津神 中祭以上の私祭の前に、神饌を供えておまつりする習わしになっています。
 祖霊社
祖霊社終戦後の昭和22年、成蹊学園内の鹿島神社の社殿を移築したもので、氏子中の戦没者・祖霊をお祀りしています。
 弓道場
弓道場武徳殿と同様、戦時期の昭和17年に修養道場として開設されたものを引き継いでいます。
 武徳殿
武徳殿剣道および柔道場です。戦時期の昭和17年に修養道場として開設されたものを引き継いでいます。
 二郎杉
二郎杉境内で2番目に大きな杉なので、二郎杉と呼ばれています。高さ40m、樹齢は700年とみられています。
 神庫
神庫 宝庫
宝庫 鏡石
鏡石本殿裏にある直径80cmほどの円形の石です。要石に比べて無名に近い石ですが、本殿と御神木を結ぶ一直線上にあり、磐境の一種との見方もあります。
 摂社 三笠社
摂社 三笠社御祭神 三笠神 鹿島神宮が鎮座する三笠山の地守の神をお祀りしています。
 大鳥居
大鳥居東日本大震災により倒壊した御影石の鳥居に替わり、境内に自生する杉の巨木を用いた同寸法の鳥居が平成26年6月1日に再建されました。
 末社 稲荷社
末社 稲荷社御祭神 保食神 - 車祓所
交通安全の御祈祷をされた方は、こちらで自動車のお祓いをお受けいただけます。
 末社 須賀社
末社 須賀社御祭神 素盞嗚尊 天照大御神の弟神である素盞嗚尊をお祀りしています。
 末社 熊野社
末社 熊野社御祭神 伊弉諾命
事解男命
速玉男命 末社 祝詞社
末社 祝詞社御祭神 太玉命  坂戸社・沼尾社遥拝所
坂戸社・沼尾社遥拝所摂社の坂戸社・沼尾社は離れた場所にあるため、こちらから遥拝することができます。
 末社 津東西社
末社 津東西社御祭神 高龗神・闇龗神
御手洗池口鳥居
東日本大震災より9年と5か月の時を経てついに鹿島神宮の御手洗池口の鳥居が竣工となりました。 鋼板製ながら木造鳥居の様式にならい部材元末の直径差を再現。 奉納者発案により銘板および沓石(亀腹石)にQRコードを設置しております。樹叢
鹿島神宮の樹叢は、茨城県指定の天然記念物です。広大な森には杉のみならずシイ・タブ・モミの巨樹が生い茂り、その種類は600種以上にも及びます。生育南限と北限の植物が混ざっているのも大きな特徴です。
要石
地中深くまで埋まる要石が、地震を起こす鯰の頭を抑えていると古くから伝えられています。水戸の徳川光圀公がどこまで深く埋まっているか確かめようと7日7晩にわたって掘らせたものの、いつまで経っても辿り着くことができなかったばかりか、怪我人が続出したために掘ることを諦めた、という話が黄門仁徳録に記されています。
御手洗池
1日に40万リットル以上の湧水があり、水底が一面見渡せるほど澄みわたった池です。昔は参拝する前にここで禊をしました。現在では、年始に200人もの人々が大寒禊を行います。
摂社 奥宮
御祭神 武甕槌大神荒魂 現在の社殿は、慶長10年(1605)に徳川家康が関ヶ原戦勝の御礼に現在の本殿の位置に本宮として奉納したものを、その14年後に新たな社殿を建てるにあたりこの位置に遷してきたものです。
奥参道
奥宮に向かって300m程伸びる奥参道は鬱蒼とした巨木に覆われ、荘厳な雰囲気を醸し出しています。
5月1日には流鏑馬神事が執り行われます。鹿園
国譲り神話において、鹿の神である天迦久神が、天照大御神の命を武甕槌大神に伝える重要な役割を担ったことから、現在でも鹿が神の使いとして大切にされています。また、奈良に春日大社を創建する際も、鹿島の神様の御分霊を鹿の背中に乗せてお遷ししたと伝わり、その道中には江戸川区「鹿骨」など鹿に関する地名が今も残っています。
御神木
鹿島神宮の森で最も古く、最も大きい木がこのご神木です。高さ約40メートルに及ぶ杉で、樹齢は約1,300年を数えます。
芭蕉句碑
「この松の実生(みばえ)せし代や神の秋」という『鹿島紀行』中の句が刻まれています。
親鸞上人旧跡
末社 熱田社
御祭神 素盞嗚尊・稲田姫命 須賀社と同じく素盞嗚尊をお祀りしています。明治以前は七夕社といっていました。
鹿島神宮園地御手洗公園
池や遊歩道が整備された静かな公園です。江戸時代までは御手洗涼泉寺がありました。
末社 大黒社
御祭神 大国主命 明治以降に鎮座された比較的新しい社です。夏越祓の日、西瓜を供えて参拝する習わしがあります。
祈祷殿・社務所
建物内に神殿を備えており、大勢の方に快適な環境で御祈祷をお受けいただけます。神職が普段仕事をする社務所もこの中です。
楼門
授与所
多くの種類の御守・御札等を授与しております。
授与時間 毎日8:30~16:30 摂社 高房社
仮殿
元和4年(1618)、社殿造営のため徳川2代将軍秀忠公が奉納しました。まずこの仮殿に神様をお遷ししてから、旧本殿を奥宮まで曳いていき、その跡地に新しい社殿を造営したのです。
江戸時代は楼門を入った真正面にあり、その後2回の移動で現在の場所となりました。
本殿・石の間・幣殿・拝殿
さざれ石
工作場
境内の木造造作物を一手に担う工作場です。
末社 御厨社
祖霊社
終戦後の昭和22年、成蹊学園内の鹿島神社の社殿を移築したもので、氏子中の戦没者・祖霊をお祀りしています。
弓道場
武徳殿と同様、戦時期の昭和17年に修養道場として開設されたものを引き継いでいます。
武徳殿
剣道および柔道場です。戦時期の昭和17年に修養道場として開設されたものを引き継いでいます。
二郎杉
境内で2番目に大きな杉なので、二郎杉と呼ばれています。高さ40m、樹齢は700年とみられています。
神庫
宝庫
鏡石
本殿裏にある直径80cmほどの円形の石です。要石に比べて無名に近い石ですが、本殿と御神木を結ぶ一直線上にあり、磐境の一種との見方もあります。
摂社 三笠社
御祭神 三笠神 鹿島神宮が鎮座する三笠山の地守の神をお祀りしています。
大鳥居
東日本大震災により倒壊した御影石の鳥居に替わり、境内に自生する杉の巨木を用いた同寸法の鳥居が平成26年6月1日に再建されました。
末社 稲荷社
御祭神 保食神 車祓所
交通安全の御祈祷をされた方は、こちらで自動車のお祓いをお受けいただけます。
末社 須賀社
御祭神 素盞嗚尊 天照大御神の弟神である素盞嗚尊をお祀りしています。
末社 熊野社
末社 祝詞社
御祭神 太玉命 坂戸社・沼尾社遥拝所
末社 津東西社
Googleストリートビュー
Googleストリートビューは、撮影したルートに沿って実際にその場にいるかのように周囲360°を見渡すことができるGoogleマップ付随の機能です。大鳥居や楼門、本殿はもちろんのこと、要石や御手洗池まで網羅されており、荘厳な神宮の境内を余すところ無くご覧頂けます。